10代のみなさんに贈る 吉村昭ブックリスト
ポーツマスの旗
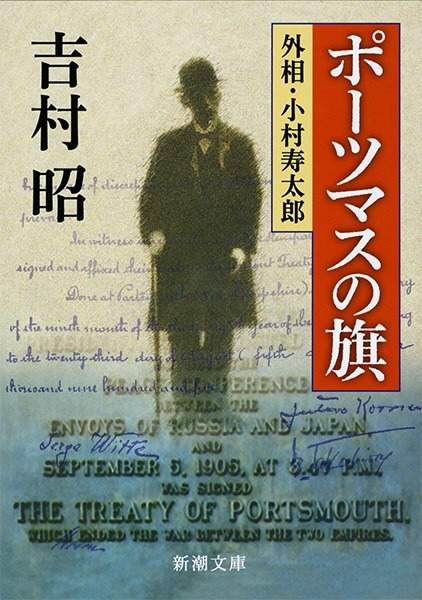
- 新潮社
- 2013年2月
誰もが勝てないと思っていた日露戦争の数々の戦いで、大きな犠牲(ぎせい)を払い勝利した日本。国民の期待に反し、ロシアの頑(かたく)なな姿勢から大きな金銭や利権などを得るのは絶望的な状況のなか、外相・小村寿太郎(こむらじゅたろう)はポーツマス講和会議でロシアとの緊迫(きんぱく)の交渉に臨(のぞ)む。
戦艦武蔵

- 新潮社
- 2009年11月
戦艦「武蔵」は日本海軍の夢と野望をかけて、昭和13年から4年余の歳月をかけて極秘裏に建造された。不沈と信じられた巨大戦艦「武蔵」はどのようにしてつくられ、戦い、海に沈んでいったのか。ちなみに、吉村昭記念文学館には「武蔵」のプラモデルが展示されている。
脱出
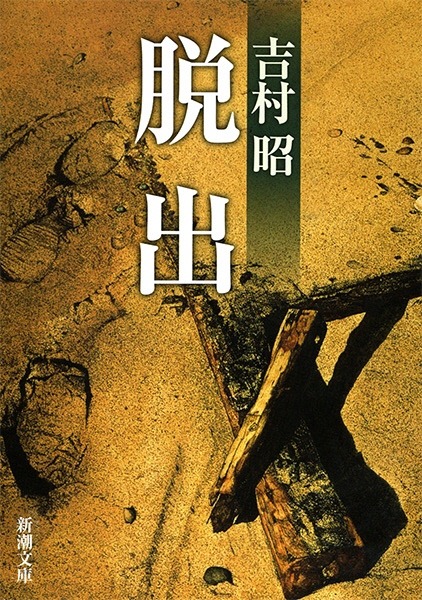
- 新潮社
- 2013年2月
戦時を背景とした短編を収録。突然のソ連の参戦に動揺し、樺太から北海道へと脱出する村人たちを追った表題作「脱出」や、沖縄から鹿児島へ向かう学童疎開船が米潜水艦に撃沈(げきちん)され、漂流(ひょうりゅう)の末、生き残った中学生の体験談を描いた「他人の城」が載っている。
東京の戦争
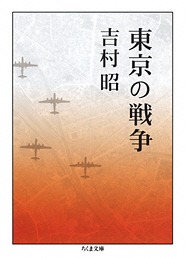
- 筑摩書房
- 2005年6月
自身の戦争体験や戦中戦後の東京下町の暮らしを綴った作品。自宅の物干し台で凧(たこ)揚げをしている時に東京初空襲のB25を目撃した話や、東京開成中学校時代に汽車に乗り、ひそかに山梨県まで一人旅を楽しんで葡萄(ぶどう)を食べた話も載っている。
少年の夏 「教科書に載った小説」より

- ポプラ社
- 2012年10月
敏夫と照子の幼い兄妹は、父が道楽で飼い始めた鯉(こい)と庭の池で遊ぶことが夏休みの楽しみであった。が、ある事件をきっかけに父は情熱を注いだ池をつぶし、鯉を手放すことになり……。
同居 「中学生までに読んでおきたい日本文学5 家族の物語」より
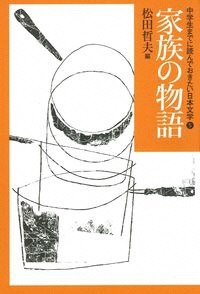
- あすなろ書房
- 2011年1月
平瀬は紹介された美しくつつましい女性と交際し、結婚を考えていた。しかし、一人暮らしの彼女の家で彼女が同居しているモノと出会い、結婚をやめることにした。彼女が同居していたモノとは一体?
見えない橋 「中学生までに読んでおきたい日本文学1 悪人の物語」より
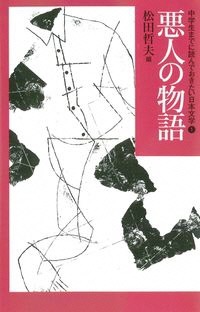
- あすなろ書房
- 2010年11月
刑務所から釈放(しゃくほう)された人の社会復帰をサポートする「保護会」のリーダー・清川に、69歳の受刑者・君塚(きみづか)を受け入れてほしいと依頼が届く。しかし、君塚は36回も、刑務所を出ては捕まることをくり返していた。それはまるで刑務所に戻りたがっているかのようで……。
冷い夏、熱い夏
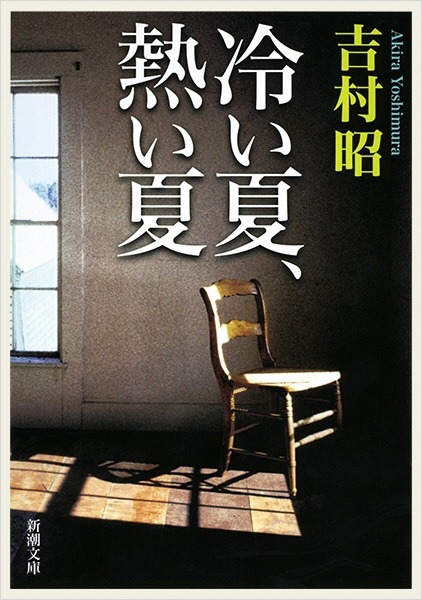
- 新潮社
- 2013年11月
働き盛りの弟を突然癌(がん)が襲った。私はその事実を弟に隠し通すことを決意し、厳しい闘病(とうびょう)生活の末待っているものは死のみであることを悟られないように振る舞う。実弟の闘病とその死を見つめた夏を克明(こくめい)に描いた作品。
星への旅
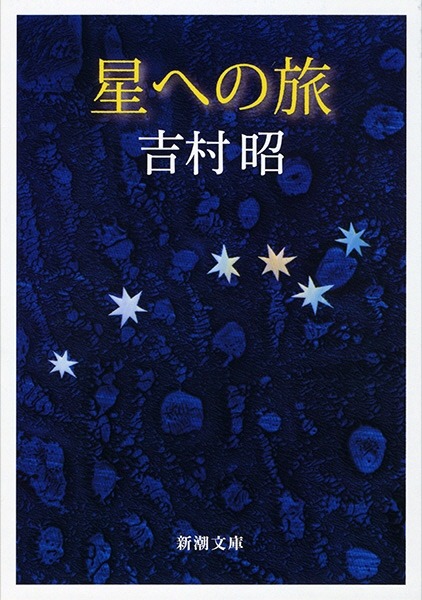
- 新潮社
- 2013年10月
トラックの荷台に揺られ、北国へ。星がまたたく空の下、海を望む断崖絶壁(だんがいぜっぺき)にたたずんだ。実際に起きた集団自殺をヒントに、吉村昭が描いた「死」。崖の上の彼らが、その後取った行動とは?第2回太宰治賞を受賞した吉村昭の出世作。
吉村昭の平家物語
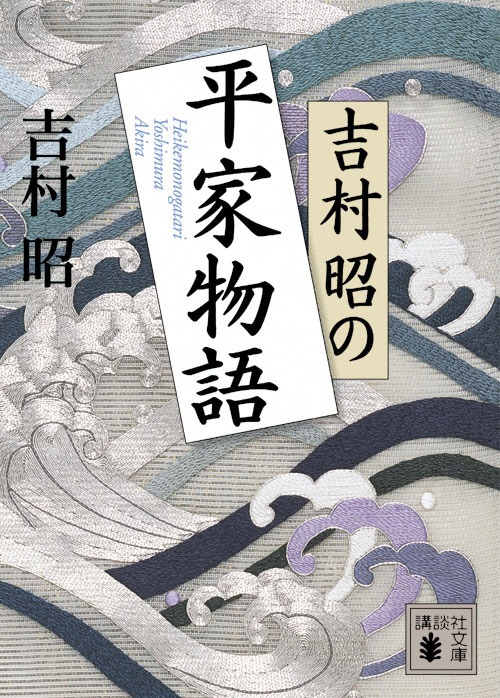
- 講談社
- 2010年1月
「祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘(かね)の声……」でおなじみの『平家物語』を現代語訳! 平安時代の終わりに栄華を極(きわ)め、滅(ほろ)びの道をたどっていく平家一族の悲しい運命を丁寧(ていねい)に描く。
『少年少女古典文学館』ver.では写真やイラストなどの解説も盛りだくさん!初心者でも安心して読める。
羆嵐
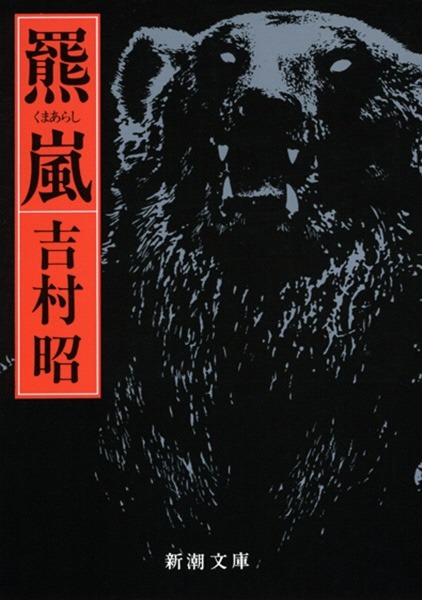
- 新潮社
- 2013年11月
北海道のとある村に凶暴(きょうぼう)なヒグマが現れ村はパニックに!死者は6名にも上り、村人たちは大ピンチ。警察もなす術がない中、一人の年老いた猟師(りょうし)が、猟銃(りょうじゅう)を手に雪山に足を踏み入れる……。大正時代に実際にあった事件を基(もと)にした物語。
破獄
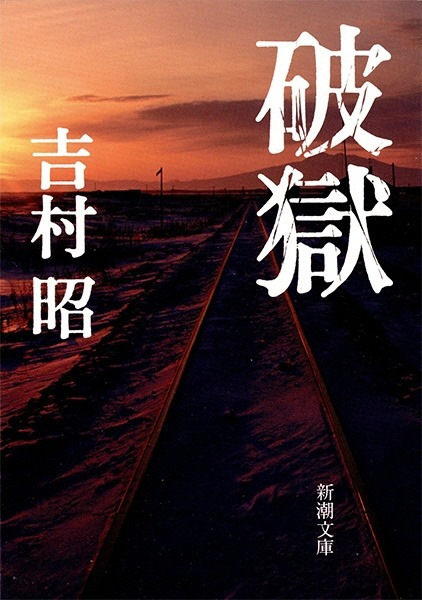
- 新潮社
- 2011年11月
青森、秋田、網走、札幌と犯罪史上未曽有(みぞう)の4度の脱獄(だつごく)を謀(はか)った佐久間清太郎。昼夜厳重な監視下におかれていたにも関わらず、脱獄を成功させた、超人的ともいえる驚(おどろ)くべきその手口とは?刑務所という閉ざされた空間の中での、看守(かんしゅ)と脱獄囚の緊迫した闘(たたか)いを描く。
海も暮れきる
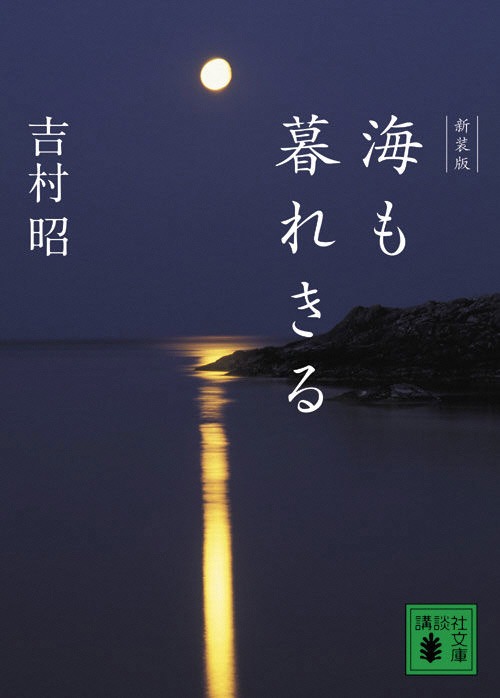
- 講談社
- 2011年5月
「咳をしても一人」など自由律俳句で知られる尾﨑放哉(おざきほうさい)。あまりの酒癖(さけぐせ)の悪さに職を失い、妻にも見放され、放浪(ほうろう)の末に流れ着いた小豆島(しょうどしま)。病に侵され死を迎えるまでの8ヶ月の孤独な日々を鮮烈(せんれつ)に描き出す。
破船
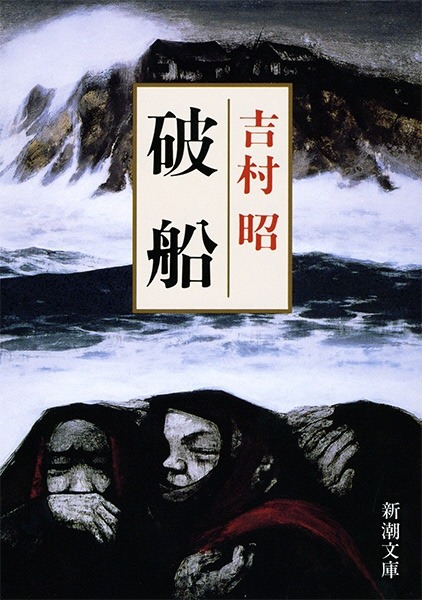
- 新潮社
- 2012年6月
極貧の村に大きな恵みを与える「お船様(ふねさま)」。それは船を座礁(ざしょう)させ積荷(つみに)を奪(うば)い取る、恐ろしい風習だった。ある冬、死人を乗せた「お船様」がやってきた。村人たちは、死人が身に着けていた上質な着物を「お船様」からの恵みとして分配すると……。
漂流
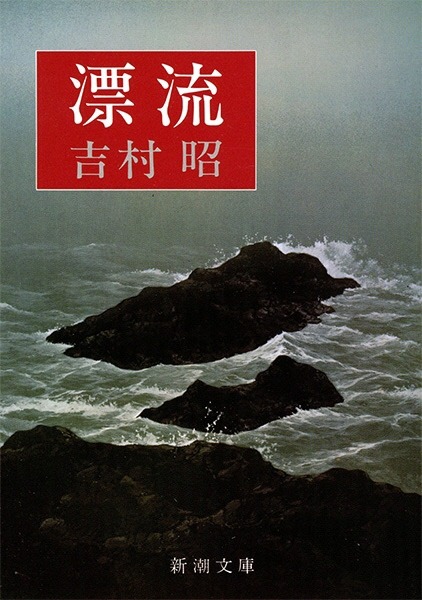
- 新潮社
- 2008年12月
江戸時代、土佐の船乗り長平(ちょうへい)は大シケにあって10日以上も漂流する。無人島に流れついたがそこは水も湧かない火山島だった。仲間が次々と倒れていくなか長平はひとり生き残り、漂着(ひょうちゃく)から12年後ついに生還(せいかん)を果たす。長平はどのようにして生き残ったのか?
朱の丸御用船
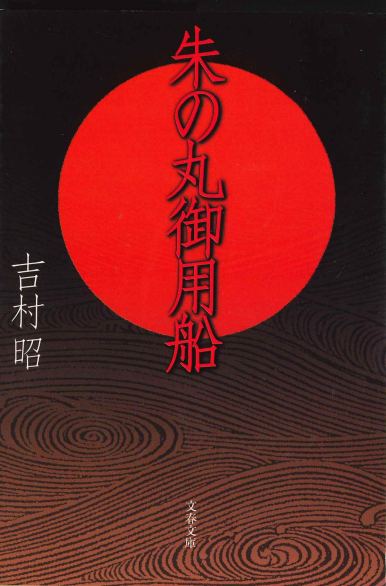
- 文藝春秋
- 2000年7月
江戸時代の貧しい村が舞台。目の前の海で難破した船から積荷(つみに)の米を盗んだ村人たち。しかしそれは幕府に年貢米を運ぶ「御城米船(ごじょうまいぶね)」であった。だれにも見られていないはずだった……。全編を通してハラハラする緊張感(きんちょうかん)があり、ミステリー好きにおすすめ。実話を基(もと)にした物語。
大黒屋光太夫 上・下
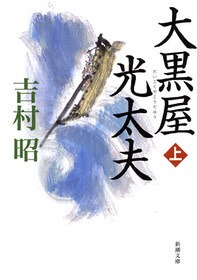
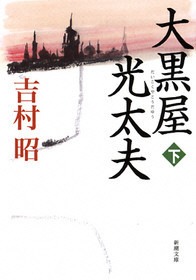
- 新潮社
- 2005年6月
時は江戸時代、1782年。船頭・光太夫(こうだゆう)は、伊勢(いせ)から江戸へ向かう道中恐ろしい嵐に遭い、船員たちとともに遭難(そうなん)。長く辛い漂流(ひょうりゅう)の末にたどり着いたのは、寒さの厳しいロシアの小島だった。日本に帰るため、光太夫たちの壮絶(そうぜつ)なロシア横断の旅がはじまる。
三陸海岸大津波
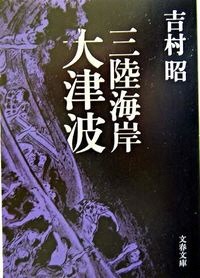
- 文藝春秋
- 2004年3月
明治29年、昭和8年、そして昭和35年。三陸海岸を襲(おそ)った3度の大津波。著者が自らの足で求めた貴重な体験者の証言や記録。自然による恐怖と、豊かさや美しさは表裏一体(ひょうりいったい)であることを改めて感じさせられる。
関東大震災
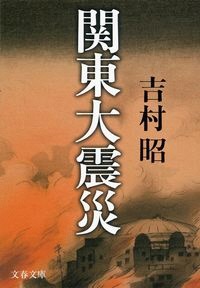
- 文藝春秋
- 2004年8月
大正12年、関東を襲った大震災。余震(よしん)におびえ、デマに惑わされ、窃盗(せっとう)や略奪(りゃくだつ)が横行し、劣悪(れつあく)な環境で感染症も流行(りゅうこう)した。震災の被害だけでなく、その後に何か起こったのかを、綿密(めんみつ)な調査と取材を重ねて執筆(しっぴつ)した。災害を知って考えるために最適な一冊。
高熱隧道
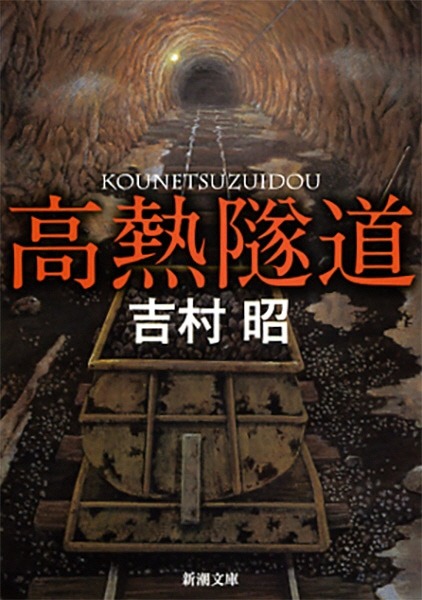
- 新潮社
- 2010年7月
昭和11年、黒部渓谷(くろべけいこく)で発電所をつくるためにトンネルの工事が始まった。掘り進むにつれて坑内の温度が上がり続け、発破(はっぱ)用のダイナマイトも自然発火してしまう。耐え難いほどの熱気の中、ホースで全身に水を浴びせながら男たちは堀り進んだ。
虹の翼
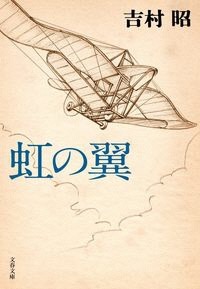
- 文藝春秋
- 2012年6月
ライト兄弟が世界最初の飛行機を飛ばす前に、日本で人を乗せて空を飛ぶ「飛行器」を考えていた男がいた。幼い頃に、家の事業が倒産(とうさん)。貧しい子供時代を経て、軍隊で看護兵になる。戦争を経験しながら「飛行器」完成に尽力した、二宮忠八(にのみやちゅうはち)の物語。
東京の下町
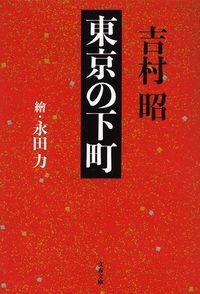
- 文藝春秋
- 2017年3月
吉村昭が子どもの頃暮らした町・日暮里。少年だった著者の目を通して描かれる昭和初めごろの街並みや、人々の暮らし。長い年月を経て変わったものはもちろん、意外と変わらないものもあったり!?今の街並みや暮らしと比べながら読んでみるのがオススメ!
事物はじまりの物語/旅行鞄のなか
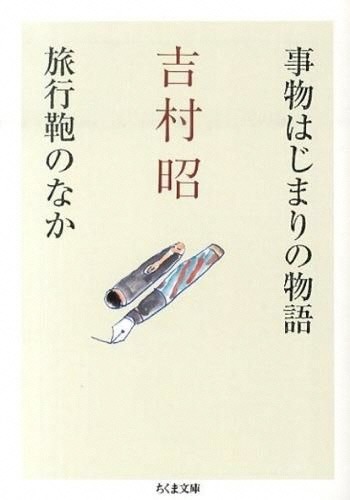
- 筑摩書房
- 2014年2月
長年の執筆活動から得た知識や経験をまとめたエッセイ集。電話など身の回りの物のはじまりを語った「事物はじまりの物語」。小説を書くための調査で出会った人々や体験をまとめた「旅行鞄のなか」。どちらも吉村昭の人となりがよく伝わってくる。
街のはなし
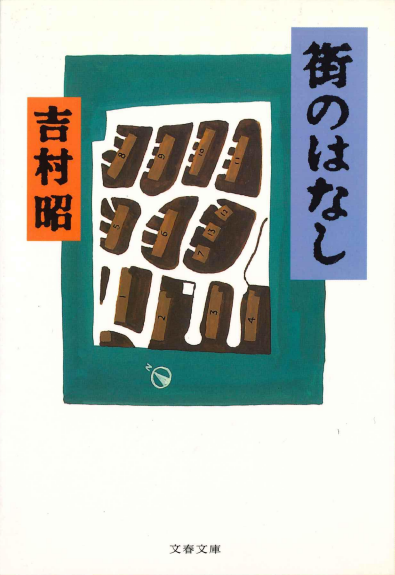
- 文藝春秋
- 1999年9月
人々の何気ない日常を鋭い視点から切り取ったエッセイ集。寮生活を送る訳あり労働者が主人公の「十七歳の少年」、飼い主の言葉と犬の行動に深く考えさせられる「告知」、小学生時代の気になる女子とのエピソードを描く「駅のホーム」など79編を収録。
