おすすめの本
SDGs入門
- 掲載日:2021年6月15日
SDGsとは、2015年に国連で定めた、持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。 17のゴール(目標)と169のターゲット(具体的な目標)で構成されています。
達成目標の2030年まで、あと10年を切ってしまいました。

日本では、例えば、「4.質の高い教育をみんなに」 は達成度が高いですが、「5.ジェンダー平等を実現しよう」、「14.海の豊かさを守ろう」 など、達成度が低いものもまだ多いです。
世界全体での達成度もまだまだ高くはありません。
SDGsについて耳にしたことがあるけど、なんだかよくわからないという方も、ゴールに向けて既に何かを始めている方も、こんな方法で目標達成に貢献してみてはいかがでしょうか。
ギフトエコノミー 買わない暮しのつくり方
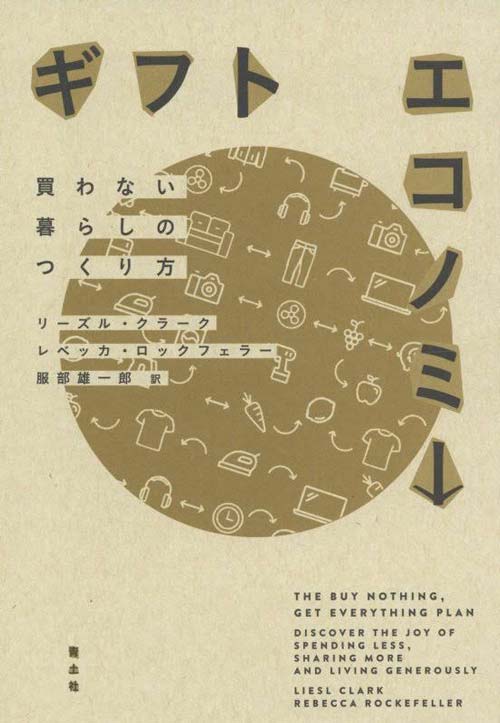
- リーズル・クラーク/著 レベッカ・ロックフェラー/著
- 青土社
- 2021年2月
「12.つくる責任つかう責任」(持続可能な生産消費形態を確保する)は、先進国で達成度が低い目標の一つです。
ゴミの日に、大量に出るゴミを見て胸を痛めたり、買ってはみたけれど、使わなくて結局ゴミにしちゃった、そんな経験をしたことがある方は、この本を読んで、「買わない暮らし」を生活に取り入れてみませんか。
買わないためには、「買う前に他のあらゆる可能性を探る」ことだそうです。
買うかわりに人に譲ってもらったり、自分で作ったり、家にある代替のものでまかなえないか、そもそも本当に必要か等々、考えてみると、買わなくて大丈夫かも、となるかもしれません。
著者の住むアメリカでは、ものを譲ったり、受け取ったり、さらに、技術や知恵さえもおすそわけする仕組みを、多くの人が利用しているそうです。
そうはいっても、商品が溢れている現代で生活していると、魅力的なあれこれを買わないなんてとても無理、と思ったら、この本で紹介されている「2度と買わない50のアイテム」からひとつ、買わない、と決めてみるのはいかがでしょうか。
例えば、ペットボトル飲料。素敵なマイボトルとちょっと良いお茶の葉を買ってみましょう。それだけでSDGsに貢献できるなんて、嬉しいですよね。
すっかり使い捨てに慣れてしまった私たちにとって、使い捨てをしない生活は不便かもしれません。
けれど、多少の不便さを受け入れないと、問題は解決しないのかもしれません。
コーヒーで読み解くSDGs
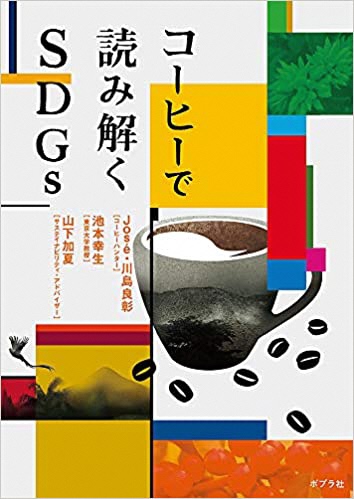
- José.川島良彰/著
- ポプラ社
- 2021年3月
近年頻繁に聞こえてくるようになった「SDGs」という言葉。「持続可能な開発目標」といわれても、いまいちピンとこないかもしれません。しかし、この目標は「全世界の国と人々が一丸となって取り組むべき目標」といわれています。
では、私たち一人一人がSDGsの達成に貢献するためには、どうしたらよいのでしょうか。そんな疑問に、私たちが毎日のように飲んでいる「コーヒー」という切り口で答えてくれる1冊をご紹介します。
例えば、SDGs第5の目標「ジェンダー平等を実現しよう」について。アフリカ・ウガンダのコーヒー農園では、土地の所有権は男性にあるという固定観念があり、その土地で育つコーヒーは「男性の作物」だという考えが根強く残っています。そのため、農園で働いていても女性の労働は無償労働とされ、金銭的に男性に依存しています。遠く離れたコーヒー生産国が抱える問題ですが、この本を通して、日本にいる私たちが「問題について知る」「コーヒーの選び方に気を付けるようになる」だけでも、改善の手助けをすることができます。
専門書を読むのはちょっと億劫だけれど、SDGsについて知りたい。個人でできることを始めたい。そんなみなさんにおすすめです。
何度でも行きたい世界のトイレ
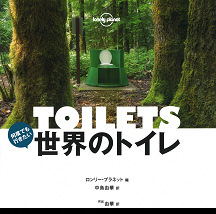
- ロンリー・プラネット/編 中島由華/訳
- 河出書房新社
- 2016年9月
SDGs17の目標の6番目は、「安全な水とトイレを世界中に」です。
今から11年前には「トイレの神様」の歌もヒットしましたが、皆さんはトイレについてどのような印象をおもちですか?
もちろん排泄(はいせつ)するために必要な場所です。また、少し頭を休めることによって忘れ物を急に思い出したり、アイデアを思いついたりする空間でもあります。 そして今やトイレに関する著作物は何冊も刊行されています。今回紹介するこちらの本では、日本のハイテクトイレやトイレ自体がアート作品になっているもの、さらに砂漠やジャングルなど様々な自然環境につくられたものなど、世界中のトイレを一冊の写真集としてまとめられています。
世界では未だ約7億人が家や近所に利用できるトイレがなく、屋外排泄をしているそうです。何らかの理由でトイレがなく、やむを得ず屋外で排泄するのは不衛生で、細菌により様々な病気にかかってしまいます。そのためSDGsの目標にもあるように、世界中のトイレの数を増やすことによって、衛生も改善され、病気にかかる人も少なくなります。
さらに大袈裟かもしれませんが、トイレ空間でのちょっとしたひらめきも多くなり、社会の発展にもつながる可能性を秘めているのではないでしょうか。
普段何気なく使っているトイレについて、少し違った視点から考えてみませんか? 世界中を自由に旅行できるのはもう少し時間がかかるかもしれませんが、山小屋のトイレやツンドラのトイレ、国立公園のトイレなどそれぞれの地に思いを馳せながら…。
なお、この本では紹介されているすべてのトイレに緯度経度が記載されているので、地図アプリ等を使用して場所の確認をすることもできます。
